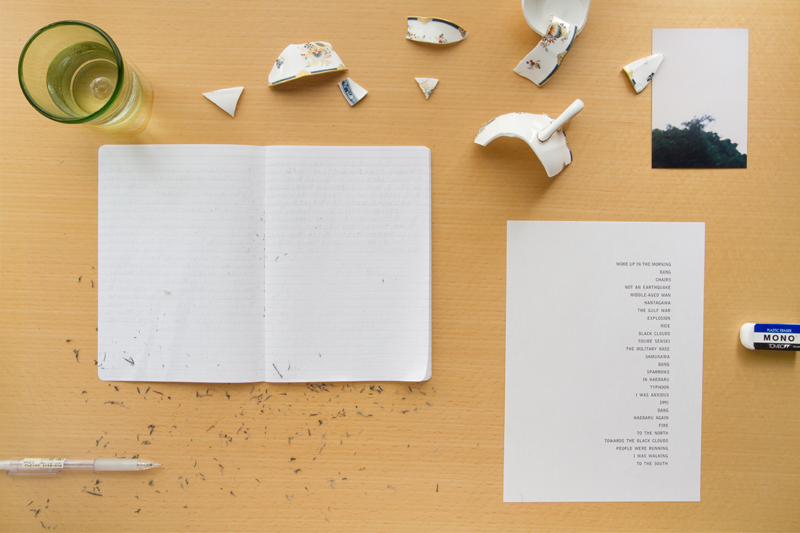Using his chalkboard, he engaged the milkman in conversations about bootleg whiskey, and even if this had made sense, the milkman wouldn’t have been able to understand, because right about this time Lefty’s English began to deteriorate. He made spelling and grammatical mistakes he’d long mastered and soon he was writing broken English and then no English at all. He made written allusions to Bursa, and now Desdemona began to worry. She knew that the backward progression of her husband’s mind could lead to only one place, back to the days when he wasn’t her husband but her brother, and she lay in bed at night awaiting the moment with trepidation.
Jeffrey Eugenides”Middlesex”(Farrar, Straus and Giroux, 2002)
うちにくる牛乳配達の黒人をジミー・ジズモと間違え、ラムの密輸に出かけるつもりで彼のトラックに乗りこむことが間々あった。黒板を使って、牛乳屋を密輸ウイスキーの話に引き込んだ。たとえ、それが意味のある話だったとしても、牛乳屋には理解できなかっただろう。というのは、そのときにはレフティーの英語力が低下しはじめていたからだ。習熟して久しい綴りや文法の間違いを犯すようになったかと思うと、英語そのものがブロークンになり、ついには、まったくできなくなってしまった。レフティーはブルサにまつわることを黒板に書くようになり、今度はデスデモーナが気が気でなくなってきた。夫の頭の中で遡行が進めば、行き着く先は一つとわかっていたからだ。それは、彼が夫ではなく、弟だった日々だった。デスデモーナは夜になると、ベッドに横たわり、おののきながらその瞬間を待った。ジェフリー・ユージェニデス(佐々木雅子訳)『ミドルセックス』(早川書房、2004年)より
アメリカにいた時はホームシックになどならなかったけれど、特定の記憶が繰り返し思い出され、帰りたくもない土地が少しずつ美化されてしまう。そんな中僕は、中学時代好きだったポップソングの歌詞をなんとなく翻訳しはじめた。中学生の頃よく聞いていて、まわりのみんな好きだったような気がするバンドの曲。
strangely sober night why am I about to cryhappiness goes onit goes on with pauses and stuttersスピッツ「スピカ」より
goodbye my sweet cloverthe story is forever asleep in the corner of my diaryスピッツ「冷たい頬」より
I want to be a cat because my words are shallowI hurt you so that you will stay by my side
スピッツ「猫になりたい」より
私は以前、通訳なら痛みがないと思っていた。でも、今はちがう。声を取り継ぐのは、本質的な語りであり、通訳の在り方には、意識の本来的姿の秘密が隠されていると思えてならない。
赤坂真理『東京プリズン』(川出書房新社, 2012)
なるほど私の国の人たちは、戦争が終わって、女のようにふるまったのではないかと。男も女も、男を迎える女のように、占領軍を歓迎した。多少の葛藤はあったとしても、相手に対して表現せず、抵抗も見せなかった。
-中略-
戦争が終わったら、日本人全体がアメリカの前に”女”になったのか、それとも、軍部を一掃したから、あとには女が残ったのか?
(同上)
通訳とは、声なき声に選ばれた、声なのだ。声なき声こそが、本質的声であり、それこそが、聞かれるべき声であるから、私はここにいる。(同上)
僕が中学生の頃、Yは海辺の家に住んでいた。特別仲が良かったわけではないけど、小さな学校だったので、みんなでよく一緒にいた。もう、イニシャルしか覚えていないかもしれない、名前も覚えていないかもしれない、そんな記憶の中の存在になっている。
中学三年夏休みの終わり頃、Yの家、一階のガレージで夕方からみんなでバーベキューパーティーをした。ブルーシールのバニラアイスを食べたあと、何となく二人で浜辺まで歩く。浜辺まで、たった1分。何故二人だったのかを思い出せば、他のみんなはとうに浜辺に繰り出していた。その時、太陽は島の反対側に沈むから残念と彼は言って、僕はもっと早く彼と仲良くなれていたはずなのにとぼんやり考えていた。二階の彼の部屋からは、海が良くみえるのだろうか。
既に夜だった。この辺には夜黄色いロープが海から伸びてきて人を海に引きずり込むらしいとか、浜辺のアダンの木は夜しくしく泣くらしいとか、ニライカナイって黄泉の国と同じって知ってた?とか、戦時中この浜に3人のアメリカ兵が漂着したらしいとか、怪談のような話がいろいろ飛び出した。アメリカ兵については、いや、それは日本兵だったはず、と別の誰かが応えたような気がする。その、兵士たちはどうなったの?島が戦争に巻き込まれないように動いて、ヒーローになったって。それから?その話あまり怖くないんだけど、と僕は思いながら、そういえば、戦争時の島の様子について聞いたことがないことに、気がついた。
うちの祖父母はどんなふうに戦争を生き抜いたのか。二人が話さないから、僕には戦争について語る言葉とその資格がないような気がしていた。他の島で起きた悲劇は海に隔てられた昔の話だった。遠かった。先生たちは、生々しい話を聞かせるけど。
怖いから今日は電気消して眠れない、とYが言ったので、皆で笑った。
二年程前、市橋達也が沖縄の離島に潜伏していたというニュースをみて、それが自分の生まれた沖縄の離島(のさらに離島)だったと聞いて、不謹慎ながら彼に興味を抱いたので、『逮捕されるまで』を読んだ。
彼が居たオーハ島は、久米島と橋で繋がった奥武島のさらに向こうにある。静かな内海を挟んだ向こうにあるその島には、かつていくらかの家族が住んでいて、子供たちは、竹馬に乗ってこちら側に渡り登校したという。僕が物心つく頃には、すでに1世帯程しか住んでないと言われていた。ずっと興味はあったけど、渡れなかった。奥武島とオーハ島の距離はそんなに無いけど、島の間、潮の流れは結構早くて泳ぎの苦手な僕は干潮時でも向こうに渡れそうになかった。何より、行く正当な理由もない。だから、僕は生まれてこのかたオーハ島に行った事がない。でも、西奥武とよばれていた、奥武島側の静かな砂浜は、僕が世界で一番好きな場所だった。海は奇麗で、観光客もいない。僕は銭湯もプールも、人がいるビーチも苦手で、水は得意ではなかった。けれど、西奥武の砂浜なら海を楽しめた。島に帰る度、かならず訪れた場所だった。地震があってからは、すこし怖くなってしまったけれど。一番好きな海、渡れない島。そこには何かあるのだろう。と、ずっと思いながら、内海の対岸から写真ばかり撮っていた。
それなのに、部外者は、何時だって軽々と境界を超えてしまう。彼はそこでどんな風景を見たのだろう。
市橋は日常を失い、それを取り戻そうとする。大阪での労働、島での潜伏。それの繰り返し。彼は、繰り返しに取り憑かれ、無人に等しい島に執着する。僕は、日常について考える。彼は島を死に場所にしたいと考えていたみたいだ。死に向かう日常。市橋達也は、沖縄で『ライ麦畑でつかまえて』を読んでいた。戦争について、島の老人から話を聞きだしたりしていた。
那覇のある本島とは違い、この島では地上戦はなかった。島には当時、まだ乗用車はなく、子どもだったおじいはアメリカの軍用車や映画を見た。山に隠れていた友軍(日本軍)は怖かったがアメリカには敵意はない。そんな話をしてくれた。
市橋達也『逮捕されるまで』(幻冬舎、2011)
そういえば島にいた頃、戦争についてあまり話を聞いた事がなかった。いくつか、事件があったことはなんとなく聞いている。あの島に戦争中、戦後何が起きていたのだろう。市橋は老人の話を聞いて、どのような「戦争」を想像したのだろう。それは、僕が思い描く「戦争」とどれくらい違うのだろう。僕たちが思うそれと、僕の死んだ祖母や祖父のそれは、どれだけかけ離れているのだろう。そう、ぼんやりと思った。
そのとき、クリント・イーストウッドがそっと逃げ出した。ぼくの豚は海に向かって走っていく。そのピンク色の鼻が暗い海の上を少しずつ移動し、燐光が頭のまわりで青い星の王冠のように輝く。
ラッタウット・ラープチャルーンサップ(古屋美登里訳)「ガイジン」、『観光』(早川書房、2010)
僕が「感光/Sight Seeing」を始めようとしてたときに、頭から離れなかった小説があって、それはラッタウット・ラープチャルーンサップの『観光』(原題:Sightseeing)」だった。タイ系アメリカ人の著者による、デビュー短編集。表題作「観光」で、視力を失いゆく母親と電車に乗って楽園へと旅をする少年が見る風景は、細長い半島をまっすぐ走る線路と、それが隔てる茶色い海、コバルトブルーの海。線路は、輝く二つの世界を分断しながらまっすぐ進む。母親にはその風景が見えていたり、見えづらかったり。
ときどき世界は薄暗く、ぼんやりしていて、水中で目を開けているみたいな感じで、再び世界が現れてくるまでにかなり時間がかかる。
同上「観光」
僕は原書の方をずっと前に読んだ。Sightseeing。観光、眺め、視界、視力、みること、目の前の風景、光。遮断、断絶。失われゆく視力、破壊される向こう側の風景、なす術も無くただ見つめること、子供の頃の記憶、そして、まだ見ぬ新世界。それらを求め、Sight(目の前の世界)Seeing(を見る行為)。写真という、届かない場所にある光を見ようとする行為。僕はこの短編集の見せる光景が、これから撮ろうとしている写真に繋がる様な気がして、新作のシリーズを「感光/Sight Seeing」と呼ぶことにした。写真が光を記憶するプロセスとしての感光と、SightをSeeingする行為。何気ない言葉遊び。そして、この作品は「American Boyfiend」へと、沖縄へと繋がって行く。
先日読んだ翻訳版の『観光』、訳者によるあとがきには、こう記されていた。
なお、本書がガイドブックのようなタイトルになったのは原題Sightseeingの通りということもあるが、それだけではない。この言葉がsight(視力、視野、光景、景色)とseeing(見ること、視覚)の合成語であり、それが表題作の内容にぴたりと合っていることをふまえ、”光を観る”とも読める「観光」にしたのである。
同上、古屋美登里「訳者あとがき」
「光を観る」。光はいつも、向こう側に、狭間に見え隠れしていて、手を伸ばせば届くものでもない。この短編集はそんな光に満ちている。徴兵抽選会の身体検査会場で男達を挑発するトランスジェンダー。クリント・イーストウッドという名のペットの子豚。闘鶏(cockfight)に熱をあげる男達、タイ語を話せないフィリピン人少年の涙、金色の歯をもつカンボジア難民の少女、故郷に住む友人とマカロニウェスタンを観ていた幸せな時期を思い涙を流す老齢のアメリカ人男性…次々に現れる、狙いなのかもよくわからない様な不思議なクィア的表象。文庫版に寄せた訳者あとがきによれば、文庫版発売現在、著者は行方が分からなくなっているらしい。また、彼の作品がどこかで読めたら、とぼんやり願っている。
2012年6月29日。那覇空港19:35発東京行き。僕はビールを飲みながら、クン・ウー・パイクのブラームスのピアノ協奏曲一番を聞いて、よしもとばななの『スイート・ヒアアフター』を読んでいた。ほろよい、甘い世界が心地よい。iPhoneでツイッターを開けば、その夜官邸前デモが最大規模になるようだった。僕はこのところ、おおい町に住む子どもがどのような思いでいるのか想像してみようとしている。1991年、湾岸戦争が始まった時僕は小学四年生で、その時母親が入院していた事もあり、那覇の繁多川に住んでいた。僕は、とても怖くて、爆弾のことばかり想像してトイレから出られなくなったりした。小さな恐怖は、だれにも届かない。大人達は、平気そうだったし、中学生の兄ふたりも何も気にしていないようだった。勇気ある人たちだなと思っていた。フェンスの向こうの人工の丘、その地下には実は核爆弾があって、いつか戦闘機がそこを爆撃して、爆発する、子どもらしく、そんなことばかり想像していた。
あの時、那覇にいたであろうアメリカ人に対しての気持ちを思い出せない。そして彼らはどう思っていたのだろう、基地に住む子どもたちは。
ふと目を上げると、前の方にアメリカ人の兵隊が10名程談笑していた。皆大きな体で角刈りだったから、きっと海兵隊員なのだろう。このなかに、結局撮影に現れなかったアンドリューがいるのかもしれない。そんな事を思いながら視線をずらすと、離れた席に一人でヘッドフォンで音楽を聴きながら本を読む青年がいた。髪型は一緒だったけど他の兵士たちより幾分華奢だった。
何を読んでいるのだろう。僕は『スイート・ヒアアフター』を読み進める。お腹に鉄パイプが刺さり一度死にかけた主人公、死んだ恋人、ゲイの隣人、沖縄人のバーテンダー。あいかわらずみんな現実離れしていてふわふわしているけれど、その世界をもすんなり受け入れられる。目の前のアメリカ人と仲良くなる事も、もしかしたらそんな風に簡単な事なのかもしれない。僕たちの関係はもっと単純なのかもしれない。でも、僕は声をかけずに飛行機に乗り込む。
「とどまる」ということが、クィア主体を構成をする複雑な可能性の一つだということを忘れるべきではない。あるクィアはクィアであるためにふるさとを離れなければならないだろうし、あるクィアは差異を保つためにふるさとの側で生き続けるのだから。
-中略-
カミングアウトの物語が、長い抑圧の時代をへて解放へ、という時間的軌道を描くかたわらで、メトロノーマティヴな物語は、主体が懐疑、迫害、秘密にみちた場所での生活に耐えたあと、寛容な場所へ、という「いなか」から「都市」への空間の移り変わりを表す。
Judith Halberstan(著者訳)『In a Queer Time and Place』(NYU Press, 2005)
ジュディス・ハルバースタムは、「都市」を「可視」と直結させ、そこにゲイ/レズビアン主体の規範が形作られる流れをメトロノーマティヴィティと呼んだ。その都市志向規範に逆らうように、いなかに残り、クィアで居続けること。たとえばネブラスカで、那覇で、もしくは久米島で。
僕はアメリカにいた頃、今よりずっと若くて、Bright Eyesが大好きで、彼らのルーツを知るためにネブラスカを訪れる程だった。ネブラスカは、ブランドン・ティーナが生きた州でもある。田舎で育った自分が感じた閉塞感に近いけどちょっと違う感情を彼らは歌にしていた。行ってみると、そこは本当に何も無くて、ただただトウモロコシ畑が広がっていた。広い所で感じる閉塞感とはどのようなものなんだろう。夕日が大きくて奇麗で、まっすぐな地平線に太陽が沈むところを生まれて初めて見たのもその時。そんな場所で、クィアでいること。ここ、ゲイバーなんだよ、と運転していた友人がさした場所は、田舎にありそうな平屋のバーで、チャイニーズレストランだと言われても頷いていただろう。あっという間に窓の向こうへと消えていった。
そんな事を思い出しながら、久しぶりにBright Eyesを聞いていた。彼の歌はクィアな存在に寄り添っていた。もしかしたらそれは、都甲幸治+柴田元幸対談(新潮 2012年7月号)、で柴田氏が言う「人種やジェンダー、階級とかじゃなくて、もっとなんとなく馴染めない人とか、『友達の少ない人』っていうマイノリティ」の部分に僕が共鳴してたからかもしれない。でも、結局Bright Eyesの「ポイズンオーク」も、田舎をでてゆくのだけれど。
ポイズンオーク ちいさな勇者
まだ電話が 紐のついた空き缶だったころ
-中略-
女装した君のポラロイド
見られて恥ずかしかったの そんな風に隠して
でもね あの時ほど君を愛おしいと思った事はなかった
-中略-
君はここを離れて良かった 僕は何処にも行けない
僕の服は 君のお兄さんの涙で濡れたまま
Bright Eyes ‘Poison Oak’ (Saddle Creek, “I’m Wide Awake It’s Morning”, 2005)
2012年6月末。梅雨があけた沖縄。僕はバスに乗り宜野湾の嘉数高台公園へ。初めて来た。岡の上、展望台の頂上に登り、しばらく汗が引くのを待ってから普天間基地を見下ろして、何枚か写真を撮り、丘を下る。バス停に向かっていると軍用飛行機が頭上の低い所を飛んでいった。写真に撮らなきゃ…と思いながら、暑さで億劫に感じ、何もせず丘を下る。歩きながら僕は、クリス・バーデンの「747」を思い浮かべていた。
“At about 8 am on a beach near the Los Angeles International Airport, I fired several shots with a pistol at a Boeing 747.”
Chris Burden. Los Angeles, California, USA; January 5, 1973.
ロサンゼルス国際空港に一番近いビーチをGoogleマップで探すと、滑走路の先端から1キロ強。数学はよくわからないけれど、ウェブでざっと調べてみたら、ボーイング747は離陸後15度の角度で上昇し、6.5秒で高さ10mに達するそうだから、同じ角度で上昇を続けた場合、滑走路から1キロ先にあるビーチから見上げた747の高度は270m弱。バーデンが使ったピストルの種類はロームのRG14(22口径)で、のちにレーガン暗殺未遂事件に使われたものと同一、サタデーナイトスペシャルと俗に呼ばれる粗悪なものらしい。銃弾の飛距離がどれ程かは分からないけれど、ピストルの射程は38口径でも50m程だそうで、飛行機の真下からでも、飛行機が静止していても届かない、粗悪な22口径のピストルならなおさら。カリフォルニアで、旅客機に向けて届きもしない銃弾を放つ行為。または、ジーンズを履いたままフォルクスワーゲンの上キリスト磔刑のまねごとをしたり、友人男性に自分の左腕を撃ってもらう行為。なぜ性能の良いピストルを使わなかったのだろう、なぜ裸にならなかったのだろう、なぜ愛する人に銃を構えさせなかったのだろう。自慰的につけられた傷はいつか癒える。そんな痛みに何の意味があるのか僕には分からない。元恋人が自分の胸に向かって矢を構えたり、男性たちの視線に曝されながら少しずつはさみでシャツを切り取られる方が、ずっと痛切だ。
普天間の空、RG14みたいなオンボロでも撃ったら届くかもしれない距離で飛行機が飛んでいった。でも、沖縄で銃は所持出来ないので、想像してみることしか出来ない。小学生が、エアガンを、ゴム銃を、パチンコ玉を、石ころを、軍用機に向けて放つ。写真にドキュメントされる事も無く、そっと放たれたひ弱な意思たち。もしかしたら、それらの一つが、ポンと音を立てて機体に触れていたかもしれない、そんな風景。
Futoshi Miyagi 2011-2013